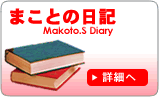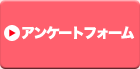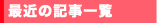« ドメスチック・バイオレンス対策について(2004年9月議会) | メイン | 長期的な住宅政策の必要性について(2005年2月議会) »
2004年10月01日
安心・安全で快適なまちづくりなごや条例についての反対討論(2004年9月議会)
◎斎藤亮人議員
1点目として、この条文の性格を示す前文は非常に問題があるということです。
17世紀に名古屋の基礎ができたという歴史認識は問題です。名古屋市が編さんした名古屋市史を見ても、17世紀以前からの生活の営みは確実に存在していることがわかります。17世紀以降、つまり徳川家という区切り方は、世界各国で先住民たちの存在を軽視してきた歴史観と通じるものがあります。また、災いをチャンスに変える志とか、地道な協働の努力が名古屋市民の伝統という評価は、行政の一方的な言い方ではないでしょうか。伝統という言葉はもっと大切にした方がいいと思います。
2点目は、条文の中に、すべての市民が主体的にまちづくりにかかわることという規定があるように、地域住民の主体性を条例で規定するのは本末転倒だということです。主体性をわざわざ規定すること自体、この条例が目指す協働というもの、また、その前提にある市民参加というものの理解が間違っていると言わざるを得ないのです。だからこそ、犯罪に遭わないように努めるなどという妙な条文を生んでしまっているのです。このような条文を認めるならば、名古屋市の進める協働というもの自体、問い直す必要があると思います。
3点目として、今回の条例制定により実効性がどのように担保されるのか、明確でないということが問題です。私は、委員会の議論を経てもこの疑問は解決しませんでした。法律、今までの条例、そして今回の条例と屋上屋を重ね、3階建ての構造は実効性の筋道をますます見えにくくするだけです。このような内容の条例であれば、今制定する状態なのかどうか疑問です。附帯決議の内容を見ても、今条例を制定するには議論不足だということを露呈しています。具体的なことを別に決めるというのみでは白紙委任の状態です。責任を持って判断できる状態ではありません。